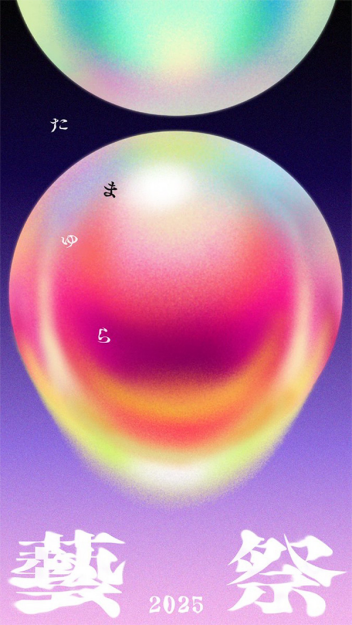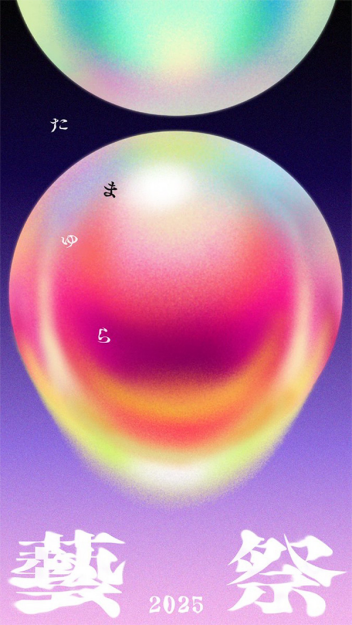TOPICS
注目記事
円山・四条派という俯瞰したテーマのもと、かつてない規模で一堂に会する展覧会「円山応挙から近代京都画壇へ」が公開されました。
巨匠・円山応挙からはじまった円山派、応挙と与謝蕪村から学んだ呉春が興した四條派は近世から近代まで美術史に大きな影響を与えました。
本展では、応挙から呉春、そして竹内栖鳳や上村松園までの画家50名、約100点で二派の系譜をたどります。
見どころは、展示室の空間を贅沢に使った円山応挙「松に孔雀図」や呉春「四季耕作図」などの立体展示。
応挙をはじめ一門の画家たちの襖絵があることから“応挙寺”ともよばれる、兵庫県・大乗寺に所蔵されている作品をX型にクロスさせ、客殿各室の襖絵を再現させたような巧妙な展示方法は見もの。

円山応挙 重要文化財「松に孔雀図」 寛政7年(1795) 兵庫・大乗寺蔵 東京展のみ・通期展示
呉春 重要文化財「群山露頂図」天明7年(1787) 兵庫・大乗寺蔵 東京展のみ・通期展示
「松に孔雀図」においては、金屏風に墨一色で描かれているものの多色に見えるのは、濃淡を巧みに利かせているため。
応挙は実物写生を追求し、それまではやまと絵や中国画が基本だった日本絵画の常識を覆した革命者。
人物画にいたっては、人間のもつ構造にも注目し、骨格から学び描いていったというほどで円山派の特徴でもあるといいます。
そんな写生の名手である、応挙の多彩な技法が余すこと発揮された名画の奥深さを堪能してもらおうと、ライティングの工夫を重ねているのだそうです。
本展では雄大で情緒ある自然、風流な趣の人物、生き生きとした動物たちが描かれ、それぞれを対比することで二派の違いも見て取れます。


岸竹堂「猛虎図」 明治23年(1890)千總蔵 東京展前期展示
左が重要美術品の円山応挙「江口君図」寛政6年(1794年) 静嘉堂文庫美術館所蔵
見ごたえある多数の屏風絵も並び、大作が目白押し。
さらには森寛斎をはじめとした円山派と四條派の28名による「魚介尽くし」の展示も。

左が「魚介尽くし」 明治5~6年(1872~1873年) 東京展では通期展示
一見、一人の画家が描いたように一つの画面が統一的に描かれ、見事に調和した合作です。
名画からあまり知られていない作品まで、一つひとつに宿る豊かな表現力をしっかりと感じられる展覧会となっています。
前期(9月1日まで)と後期(9月3日から)では大幅な展示替えもあり、会場内には、大乗寺襖絵のVRも。
ミュージアムショップには、可愛らしいオリジナルグッズが多数揃うので、こちらもお見逃しなく!
円山応挙から近代京都画壇へ
■会期 2019年8月3日 (土)~9月29日(日)
※前期は9月1日(日)まで、後期は9月3日から。前期と後期で大幅に展示替え
■開館時間 10:00~17:00(入館は閉館の30分前まで)
■会場 東京藝術大学大学美術館
■休館日 毎週月曜(祝日または振替休日の場合は開館、翌日休館)
■料金(税込) 一般1,500円/高校・大学生1,000円
■公式サイト https://okyokindai2019.exhibit.jp/(外部サイトにリンクします)